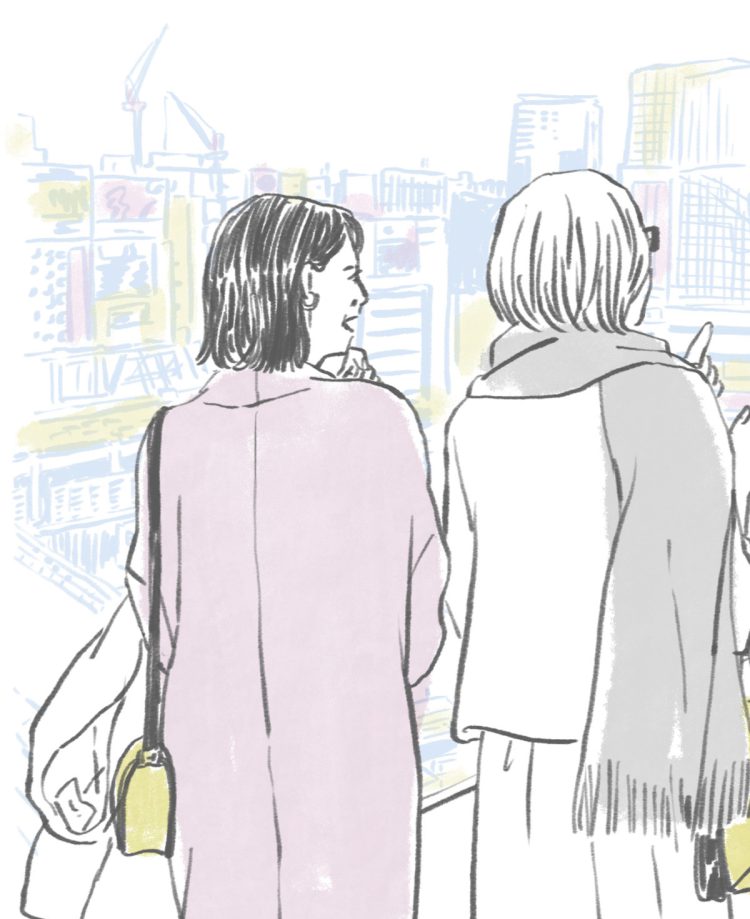第1話:「れ、ん、あ、い」
食後のコーヒーがほぼ飲み干される頃になっても、紗也華はまだ、話の勢いを失ってはいなかった。
「ドタキャンされるのって、本当に嫌じゃない? 人の時間をなんだと思ってるのって思うし、家帰っても結局ずっと考えちゃうし」
「ああ、確かにねえ」
わたしは相づちを打つが、会えるはずだった日にキャンセルされた経験も少なければ、帰宅後にもずっと誰かのことを考えてしまった経験なんてほぼ皆無なので、説得力はないだろうと思う。でも多分、紗也華もこちらの事情は理解している。そのうえでなお、聞いてもらいたいのだろう。話を吸収するスポンジが必要なのだ。
「やっぱり、別れるわ」
紗也華は言い、黒い液体がわずかに残る目の前のカップを見つめる。今日だけでも何度となく聞いた言葉だった。
でもなあ、と言うに違いない。そう予想して、何も答えずにいたら、でもなあ、と紗也華が言い出すので、わたしはつい小さく笑ってしまう。紗也華は、自分が同じ流れを繰り返してると気づいたのか、なんで笑うの、と言い返しつつも、やはり少し笑っていた。そして言った。
「いずみはどうなの、最近」
突然質問の矛先を向けられ、どう答えていいものか迷ってしまう。答えをひねり出した。
「新しく入った山脇さんって子と組んでやってる仕事があるんだけど、一人では思いつかないアイディアをいろいろ出してくれるから、かなり助かってる。コンペ仕事だし、どうなるかわかんないけど。ただ」
「仕事じゃなくって」
いけそうな気もするんだよね、という続きはさえぎられた。紗也華がなおも言う。
「恋愛だよ。れ、ん、あ、い」
まるでこちらが、恋愛という言葉を知らないかのように言うので、また笑いそうになる。けれど同じようなものかもしれない、とも思い直す。
「ぜんっぜん」
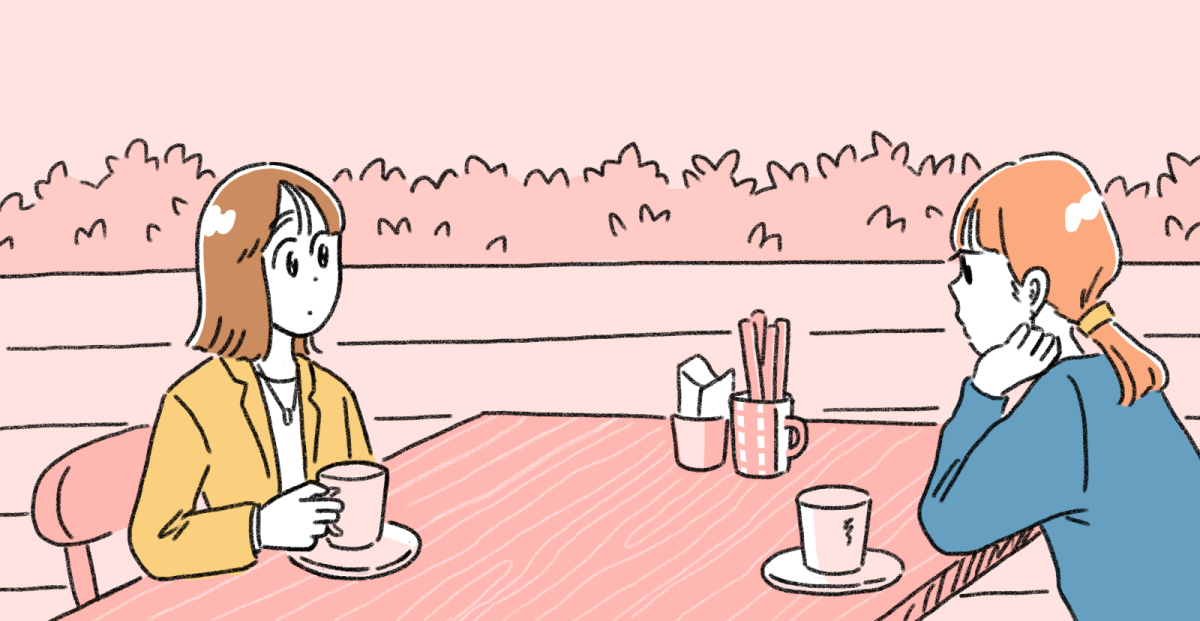
正直に答えると、相変わらず坂野先生だなあ、と言われた。
わたしたちが知り合った女子高時代から、わたしは恋愛にあまり興味がなかった。恋の悩みについては、聞く専門だったといってもいい。そんなわたしに、先生、というあだ名をつけたのが誰だったのかは思い出せない。いずみ、悟ってる感じだから、と何人もに言われたが、尊敬の念によるあだ名ではないことは、もちろんわかっていた。
「そろそろ行こっか。また来月、ヒカリエでランチしよ」
「うん」
早くも支度を始める紗也華に、慌てて続く。
相変わらず、というのなら、紗也華も同様だと思う。高校時代から、紗也華には常に好きな人がいた。中学時代の同級生、文化祭で見かけた他校の男子、世界史の先生、学校近くのコンビニ店員。わたしが把握しきれていない人もいるかもしれない。恋人がいるときでも、片思いをしているときでも、紗也華は恋にまつわる何かしらの悩みを抱え、苦しんでいて、それでいてどこか楽しそうだった。今だって。
チーズの香りが漂う店内を出て、あえてエレベーターではなく、エスカレーターを使って七階から降りていく。エレベーターよりエスカレーターのほうが好きなんだよね、とこのあいだのランチの帰りに言ったのは紗也華で、そう言われると、わたしもそんな気がした。
高校時代は二人きりで会うほど仲が良かったわけではないし、大学時代は年に一度か二度、集まりで顔を合わせる程度だった。昨年、飲み会で再会し、どちらも渋谷で働いていることがわかり、仕事内容も、デザイン事務所と女性向けウェブサイトの編集で、なんとなく共通の話題が多く、以来、月に一度のペースでこうしてランチをとっている。路面店に行ったりもしていたが、選択肢の多い渋谷ヒカリエが定番のコースになった。
高校を卒業してから、もう十年が経つ。想像していた大人とは、だいぶ違う場所にいるような気がする。紗也華はどうなのだろう。
「やっぱり別れようと思うんだよね」
エスカレーターに乗りながら、わたしの前にいる紗也華が言う。でもなあ、と言うのを待っていたが、言葉は続かない。表情を窺うと、真剣だった。
わたしは今までに、誰かを本気で好きになった記憶がない。付き合ったことなら二回だけある。どちらも相手のことを嫌いではなかったが、相手が望むようには好きでいられなかった。
恋愛に悩む紗也華の話を聞いているとき、自分との違いに、少し安心する。恋愛の厄介さも苦しさも不自由さも、充分に伝わってくるから。そしてなぜか少し、うらやましくなる。
「ごはん、おいしかったね」
わたしは言った。紗也華は、ちょっとー、聞いてるの、と少し怒るように言ってから、それでも笑って、うん、と答えた。
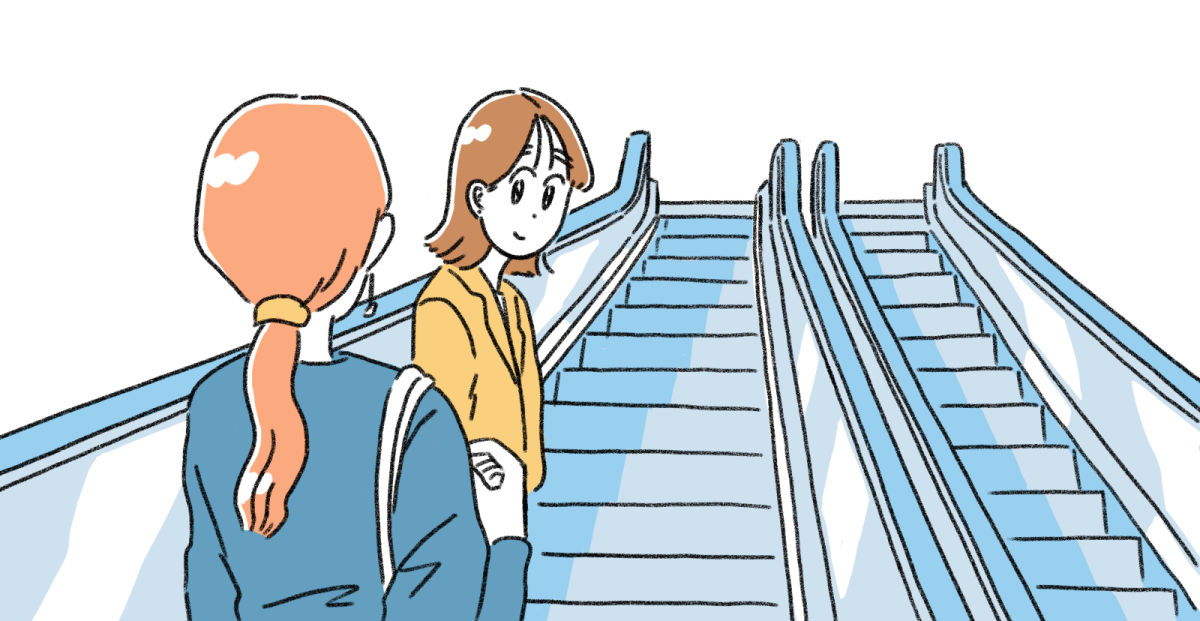
illustration : Yuki Takahashi

 最新情報はこちら
最新情報はこちら